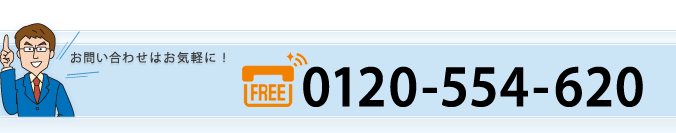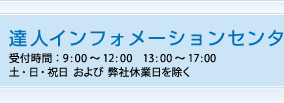【2025年度版】税制改正大綱の概要と変更点をわかりやすく解説

2024年12月に2025年度(令和7年度)版の税制改正大綱が公表されました。毎年、所得税や法人税などのさまざまな税に関する改正の方針が示されていますが、2025年度版では、どのような変更点が記載されているのでしょうか。
ここでは、税制改正大綱の概要と、各種税制の主な変更点について解説します。
目次
税制改正大綱とは、翌年度の税制改正の骨組みをまとめたもの
税制改正大綱は、翌年度の税制改正の骨組みをまとめたものです。与党の税制調査委員会が中心となって各省庁などから挙がった要望を取りまとめ、毎年12月中旬頃に公表されます。2025年度税制改正大綱は、2024年12月20日に自民党・公明党から公表されました。2025年度以降の税制については、この大綱をベースに国会で議論が行われ、法案が作成されることになります。
税制改正大綱には、個人所得課税、資産課税、法人課税、国際課税などの枠組みごとに、税制の変更点が記載されています。
個人所得課税・資産課税における主な変更点
2025年度税制改正大綱には、個人所得税・資産課税について、個人所得課税(国税)における基礎控除額や、特定扶養控除における子の年収要件などが盛り込まれています。主な変更点は、下記のとおりです。
個人所得課税(国税)における基礎控除額などの引き上げ
2025年度税制改正大綱には、個人所得課税(国税)における基礎控除額などの引き上げの改正について記載されています。これは、いわゆる年収の壁に関する改正です。給与所得者につき所得税が課税されない給与収入額が、従来の103万円から123万円へと拡充されました。
所得税が課税されない給与収入額は、基礎控除額と給与所得控除の合計額で算出します。基礎控除額については、合計所得額が2,350万円以下の個人の基礎控除額が58万円となり、これまでより10万円拡大されました。また、給与所得控除ついても、55万円の最低保障額が65万円となり、10万円引き上げられています。
特定扶養控除における子の年収要件の引き上げ
子供の特定扶養控除についても、2025年度税制改正大綱に改正内容が盛り込まれています。従来、子供の給与収入が103万円以下の場合に扶養控除が適用される制度でしたが、2025年度版税制改正大綱において、103万円を超えても段階的に控除を受けられる特別親族控除(仮称)が新設されました。
子供がアルバイトなどで受け取る給与が年間150万円に達するまでは、従来の制度と同じ63万円の扶養控除が受けられます。また、150万円を超えても控除額が0円になるのではなく、給与金額の増加に合わせて控除額が減少していく仕組みが導入されています。
そのほかの変更点
2025年度版税制改正大綱の個人所得課税・資産課税の分野では、上記で解説した項目以外にも、さまざまな税制改正が予定されています。下表はその一例です。
■2025年度版税制改正大綱の個人所得課税・資産課税の主な変更点
| 変更点 | 変更の内容 |
|---|---|
| 生命保険料控除の拡充 | 23歳未満の扶養親族がいる世帯(子育て世帯)につき、新生命保険料に関する一般生命保険料控除の適用限度額を4万円から6万円に引き上げ |
| 住宅ローン控除の拡充 | 夫婦のいずれかが40歳未満の場合、または19歳未満の扶養親族がいる場合について、控除対象借入限度額を上乗せ <控除対象借入限度額の変更点(2025年入居の場合)>
|
| 事業承継税制の要件の緩和 | 後継者の役員就任、事業従事の時期の要件につき、いずれも贈与の直前までに緩和(改正前は、贈与の日の3年以上前に役員に就任し、事業に従事していたことが求められていた) |
| 生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置の延長など |
|
法人課税における主な変更点
法人課税分野でも、さまざまな変更点が2025年度税制改正大綱に記載されています。代表的な変更点は下記のとおりです。
中小企業者の法人税の軽減税率の延長など
2025年度税制改正大綱で、中小企業者の法人税の軽減税率について、期限の延長と税率の改正が盛り込まれました。中小企業者の法人税の軽減税率とは、中小企業の所得金額のうち800万円以下の金額に適用される税率のことです。税制改正大綱では、この制度が適用できる期間を2027年3月31日までに開始する事業年度までとしており、2年間延長する旨が記載されています。
また、所得金額が10億円を超える事業年度については、軽減税率を15%から17%に引き上げるよう見直されました。グループ通算制度の適用を受けている法人に関しては特例税率の適用対象外となり、本則税率19%が適用される点にも注意が必要です。
中小企業関連税制の延長や制度内容の見直し
中小企業経営強化税制に関する適用期限の延長と制度内容の見直し、中小企業投資促進税制に関する適用期限の延長も、2025年度税制改正大綱に記載されています。
中小企業経営強化税制については、デジタル化設備(C類型)を除いて適用期限が2年間延長され、2027年3月31日までとなりました。また、売上100億円超を目指す中小企業については建物が対象施設に追加され、生産性向上設備(A類型)と収益力強化設備(B類型)の適用要件に関する指標も見直されています。A類型とB類型の変更点は下記のとおりです。
■中小企業経営強化税制のA類型とB類型に関する変更点
| 類型 | 変更前の要件 | 変更後の要件 |
|---|---|---|
| A類型 | 導入する設備の生産効率などの指標が、旧モデルと比較して年平均1%以上改善されていること | 生産効率などの指標について、単位時間当たり生産量、歩留まり率または投入コスト削減率のいずれかが年平均1%以上改善されていること |
| B類型 | 投資利益率が年平均5%以上となる投資計画に関する設備であること | 投資利益率が年平均7%以上となる投資計画に関する設備であること |
中小企業投資促進税制に関しては、適用期限が中小企業経営強化税制と同様に、2027年3月31日まで延長されています。
組織編成に関連する税制の明確化
組織再編に関連する税制では、非適格合併などにより移転を受ける資産などに関する調整勘定が明確化されました。債務超過などの原因で支払対価がない場合にも、資産調整勘定の金額が生じることが明確化されています。反対に移転資産などが資産超過となっており、かつ一定の資産評定を行っていない場合には、資産と負債の差額を資本金等の額の増加額とするよう定められました。
また、グループ通算制度の適用を受ける通算法人の行った株式分配について、みなし配当の金額を計算する方法が見直されるといった変更点も盛り込まれています。
その他の変更点
法人課税に関するその他の変更点として、地域未来投資促進税制の見直し・延長、企業版ふるさと納税制度の延長、リース会計基準の変更に伴う措置なども挙げられます。それぞれ、下記のような改正が予定されています。
■2025年税制改正大綱での法人課税分野の主な変更点
| 変更点 | 変更の内容 |
|---|---|
| 地域未来投資促進税制の 見直し・延長 |
|
| 企業版ふるさと納税制度 の延長 |
適用期限を2028年3月31日までとして、3年間延長 |
| リース会計基準の変更に 伴う措置 |
オペレーティング・リースにつき、従来の会計基準と新リース会計基準では処理が変わるが、税法上の処理は変更されないことが明確化。その際に生じる会計上の費用計上額と税務上の費用計上額の差は、申告時に調整 |
国際課税における主な変更点
国際課税における主な変更点として、グローバル・ミニマム課税への対応と、外国子会社合算税制の見直しが挙げられます。海外でも事業展開を行う企業は、下記の改正内容を把握しておきましょう。
グローバル・ミニマム課税
2025年度税制改正大綱には、グローバル・ミニマム課税に関連する税制の創設が盛り込まれています。グローバル・ミニマム課税とは、国ごとに最低15%以上の課税を確保するための制度のことです。同制度は下記3つのルールを基本方針として、国際的に導入が進められています。
<グローバル・ミニマム課税の3つのルール>
- ・ 所得合算ルール(IIR:Income Inclusion Rule):海外子会社などの所在地国での実効税率が、国際的に合意された最低税率(15%)を下回る場合、親会社などの所在地国で15%となるまでの差額を追加課税
- ・ 軽課税所得ルール(UTPR:Undertaxed Profits Rule):海外親会社などの所在地国での実効税率が15%未満の場合、子会社などの所在地国で15%となるまでの差額を追加課税
- ・ 国内ミニマム課税(QDMTT:Qualified Domestic Minimum Top-up Tax):国内法人の実効税率が15%未満になった場合、15%となるまで差額を国内法人に追加課税
■グローバル・ミニマム課税のイメージ

UTPRは、IIRが適用できない場合の補助的な制度に当たります。また、QDMTTの制度があれば、海外でのIIRやUTPRによる追加課税を防ぐことが可能です。
日本においても2024年から、IIRについては法制化されていました。2025年版税制改正大綱では、残る2つのUTPRとQDMTTについても法制化を行う旨が記載されています。
なお、これらのルールは直近の4会計年度のうち2年度以上にわたって、連結総収入金額が7億5,000万ユーロ以上に達した多国籍企業グループに適用されます。
外国子会社合算税制
2025年度税制改正大綱では、外国子会社合算税制の事務負担軽減を目的として、合算時期の変更と添付書類、保存書類の簡素化が盛り込まれました。グローバル・ミニマム課税に関連する制度の導入に伴い、企業の事務負担が増大する懸念があったことから設けられた措置です。
外国子会社合算税制の対象になると、外国子会社などの所得を国内の親会社に合算しなければなりません。その合算時期に関しては、従来は外国子会社の事業年度終了日の翌日から2ヵ月を経過する日を含む親会社の事業年度に合算することとされていました。改正後はこのうち2ヵ月の要件が4ヵ月に緩和されます。
添付書類、保存書類の簡素化については、株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書、貸借対照表と損益計算書に関する勘定科目内訳明細書の添付・保存が不要となりました。ただし、従来から添付・保存が義務づけられていた貸借対照表・損益計算書、本店所在地国の法人所得税の申告書およびその他の書類(株主名簿など)に関しては、引き続き添付・保存する必要があります。
消費課税における主な変更点
2025年度税制改正大綱には、消費課税に関する変更点として、消費税の外国人旅行者向け免税制度に関する見直しが盛り込まれています。
例えば、免税店が外国人旅行者に免税対象品を販売した際の免税方式として、リファンド方式の導入が予定されています。リファンド方式とは、商品販売時に免税店が外国人旅行者から消費税相当額を預かり、その消費税額については、出国時に販売した商品の持ち出しが確認された場合に限って返金される仕組みのことです。免税対象品を免税価格で購入したにもかかわらず、国外に持ち出されないといった不正を防止するための変更点といえます。
また、免税対象物品の範囲についても下記のように見直しが行われました。
■免税対象物品の範囲に関する主な変更点
| 変更点 | 変更の内容 |
|---|---|
| 一般物品と消耗品の区別 | 廃止 |
| 消耗品の購入限度額 | 廃止 |
| 消耗品の特殊包装 | 廃止 |
| 免税対象となる物品 | 通常生活の用に供する物品に限る要件を廃止 |
免税販売手続きについても見直されています。税抜き金額で100万円以上の免税対象品に関しては、商品を特定するためのシリアルナンバーなどを国税庁へ提出することとなりました。加えて、従来の制度では免税対象品を免税店以外から海外へ配送する「別送」が認められていましたが、この取り扱いが廃止となります。
防衛力強化に係る税制措置
2025年度税制改正大綱では、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置も講じられています。主な改正点は、防衛特別法人税(仮称)の創設と、たばこ税の課税方式の見直し、税率の引き上げです。
防衛特別法人税(仮称)の創設
防衛費にあてる財源の一部として、法人に対して、法人税額の4%相当額の付加税を課税する防衛特別法人税(仮称)が創設されることになりました。改正案では、下記の計算式にもとづいて税額を算出することとされています。
<防衛特別法人税の計算式(案)>
防衛特別法人税=(基準法人税額−基礎控除額)×4%-税額控除
基準法人税とは、所得税額控除や外国税額控除、分配時調整外国税相当額の控除などを適用せず算出された法人税額です。外国税額控除や分配時調整外国税相当額の控除などについては、基準法人税額の4%相当額を計算したあとに、税額控除として差し引くことができます。
また、基礎控除額は一律で500万円となっています。つまり、基準法人税額が500万円を超えない場合、防衛特別法人税は課税されません。
たばこ税の課税方式の見直し、税率の引き上げ
防衛費にあてる財源の確保は、防衛特別法人税のほか、たばこ税によっても行われる予定となっています。加熱式たばこの換算方法が、紙巻たばこと同等の税負担になるよう見直されることになりました。換算方法の見直しは、一度に行われるのではなく、2026年4月1日と10月1日の2段階に分けて行われます。
また、たばこ税の税率についても、特例措置によって当面のあいだ引き上げられることになりました。2027年4月1日、2028年4月1日、2029年4月1日の3段階で、1本あたりの税額が0.5円ずつ引き上げられます。
納税環境整備
2025年度税制改正大綱には、納税環境整備に関する変更点も盛り込まれました。納税者の負担軽減や利便性向上を図るための措置として、電子帳簿等保存制度の見直しやe-Taxの利便性向上などが予定されています。
電子帳簿等保存制度の見直し
電子帳簿等保存制度の変更点としては、重加算税の適用対象と、65万円の青色申告特別控除の適用要件の改正が挙げられます。
重加算税については、電子取引データの隠蔽、改ざんがあった場合に重加算税の割合が10%加算される規定があります。この規定の適用対象から、電子取引データの訂正、削除の事実や内容の確認が可能な国税庁長官が定める基準に適合するシステムを使用して、データの送受信・保存を行っているケースなどが除外されることになりました。
65万円の青色申告特別控除の適用要件に関しては、新たな要件が追加されています。従来は、優良な電子帳簿の保存または電子申告のいずれかに対応していることが必要でした。改正後はこれらに加え、上記の国税庁長官が定める基準に適合するシステムを使用していて、電子取引データの送受信・保存が行われている場合でも、65万円の青色申告特別控除が適用できるようになります。
e-Taxの利便性の向上
2025年度税制改正大綱では、e-Tax利用時のイメージデータの送信要件も改正されています。提出可能なデータ形式が増えたほか、イメージデータ作成時の要件が緩和されています。
提出可能なデータ形式については、従来はPDF形式のみが認められていましたが、2028年1月1日よりJPEG形式での提出も可能になる予定です。また、スキャナーなどで読み込んでイメージデータを作成する際に、従来は赤色・緑色・青色それぞれ256階調以上で作成することが求められていましたが、この要件が白色から黒色までの256階調以上に改められることになります。これにより、白黒で読み取ったイメージデータの提出も認められることになりました。
税制改正大綱の主な変更点を把握しておこう
本記事で解説した変更点は、いずれも税制改正大綱に記載のある情報です。今後の税制改正法案の審議などを通じて、改正内容が変更となる可能性も否定できません。例えば、いわゆる年収の壁の改正に関しては、税制改正大綱に記載のある123万円にとどまらず、178万円への拡大を目指して協議を進める動きも見られます。
税制改正では、自社が影響を受ける可能性のある変更点を確認した上で、情報収集を続けていくことも重要です。主な変更点を参考にしつつ、実際の法案がどのような形でまとまるのか、常に最新の情報を確認するようにしましょう。
監修者
石割由紀人(石割公認会計士事務所)
公認会計士・税理士、資本政策コンサルタント。PwC監査法人・税理士法人にて監査、株式上場支援、税務業務に従事し、外資系通信スタートアップのCFOや、大手ベンチャーキャピタル、上場会社役員などを経て、スタートアップ支援に特化した「Gemstone税理士法人」を設立し、運営している。
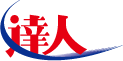


 0120-554-620
0120-554-620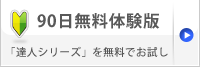
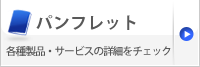
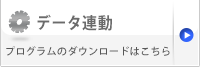
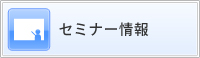
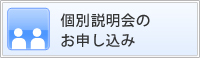
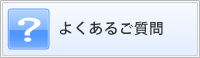
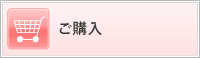
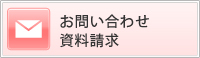



 セミナー情報
セミナー情報 個別説明会のお申し込み
個別説明会のお申し込み よくあるご質問
よくあるご質問 ご購入
ご購入