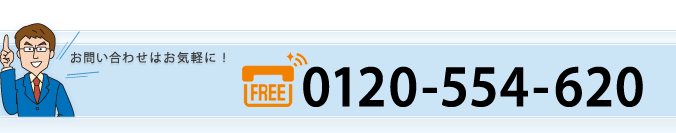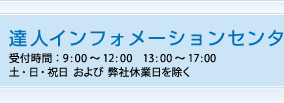給与計算ソフトとは?機能や導入メリット、選定のポイントを解説

給与計算は毎月必ず発生する業務であることに加え、正確性が求められることから、経理担当者にとって少なからず負担になりがちです。税率や社会保険料率をはじめ、労働基準法などが改正された際には漏れなく反映する必要があるため、常に最新情報を収集しなくてはなりません。その業務の効率化に便利なのが、給与計算ソフトです。
ここでは、給与計算ソフトについて、代表的な機能や導入メリットを解説します。
目次
給与計算ソフトとは、給与計算や年末調整の業務を自動化できるソフトのこと
給与計算ソフトとは、給与計算や年末調整の業務を自動化できるソフトのことです。社会保険料や税金の計算など、複雑でミスの許されない業務を効率化できます。給与計算だけでなく、給与明細の生成や賃金台帳の作成といった給与に関連するデータの管理のほか、給与振込の手配、年末調整などにも対応しているのが一般的です。
給与計算ソフトの提供形態には、大きく分けてクラウド型とインストール型の2種類があります。それぞれの主な特徴は下記のとおりです。
■給与計算ソフトの提供形態別の特徴
| 形態 | 一般的な料金体系 | インターネット環境の要否 | アップデートへの対応 |
|---|---|---|---|
| クラウド型 | 月額/年額利用料 | 必須 | 随時自動的に対応 |
| インストール型 | 買い切り | 不要 | アップデート版のインストールが必要 |
なお、給与計算に特化した機能だけでなく、人事管理を一元的に行える機能を備えているソフトもあります。
給与計算ソフトの代表的な機能
給与計算ソフトの機能は製品ごとに異なります。ここでは、多くのソフトに見られる代表的な機能を見ていきましょう。
■給与計算ソフトの代表的な機能

給与の計算
給与計算ソフトの基本的な機能として、給与の計算が挙げられます。勤怠管理のデータをもとに、残業時間や休日出勤時間などを踏まえて給与計算を自動化できます。また、税金や社会保険料など各種控除に関しても自動で算出することが可能です。従業員ごとに雇用形態や基本給などを事前に設定するだけで、煩雑な計算をすることなく毎月の給与額を正確に算出できます。
給与明細の作成
給与計算ソフトでは、算出された給与の金額にもとづき、システム上で給与明細を作成できます。ソフトによっては、従業員にWebブラウザ上で給与明細を閲覧してもらう形で配布することも可能です。給与明細を紙ベースで配布する必要がなくなるため、ペーパーレス化を促進できます。また、過去の給与明細も簡単に閲覧できるため、再発行の対応が不要になる点も長所です。
給与振込の設定
給与の振込先を従業員ごとに設定することで、振込作業を自動化できるソフトもあります。手作業で1件ずつ振り込む場合と比べて担当者の負担が軽減されるだけでなく、金額の入力ミスや振込先の間違いなどを防ぐことが可能です。
従業員からの申し出により給与の振込先口座を変更する際にも、給与計算ソフトに登録されている口座情報を更新するだけで済みます。
年末調整の管理
給与計算ソフトには従業員ごとの勤怠、給与、源泉徴収額などのデータが蓄積されているため、年間分を集計することにより年末調整にも対応可能です。
年末調整の際には、源泉徴収票などの各種書類を作成する必要があります。こうした書類もシステム上で自動生成できる機能を備えたソフトであれば、年末調整に関連する業務を大幅に効率化できるでしょう。転記ミスや計算ミスといったヒューマンエラーを防止するためにも、有効な機能です。
各種台帳の作成
給与計算ソフトによっては、賃金台帳や労働者名簿、出勤簿といった法定三帳票のほか、社会保険などの台帳を作成する機能が搭載されているソフトもあります。これらの台帳をシステム上で作成・管理することにより、作成の効率化や記載ミスの防止が期待できるでしょう。
特に従業員の入退職に伴い各種台帳で情報の追加、削除を行う際には、見落としや抜け漏れが発生しがちです。従業員のさまざまな情報をマスター登録することで、各種台帳への反映に漏れや重複が生じるのを防げます。
マイナンバーの管理
従業員のマイナンバーについては取得、保管、破棄の方法が法律で規定されていますが、給与計算ソフトによっては、法律に沿った形でマイナンバーの管理が可能です。データの暗号化やアクセス制限など、情報漏洩を防ぐためのセキュリティ機能を備えた給与計算ソフトもあります。こうした機能を活用することで、従業員のマイナンバーを効率的かつ安全に管理できます。
給与計算ソフト導入のメリット
給与計算ソフトを導入することには、さまざまなメリットがあります。代表的なメリットとしては、下記4点が挙げられます。
ミスを削減できる
給与計算ソフトは勤怠管理のデータをもとに給与を自動計算するため、手作業で集計などを行う場合と比べて人的ミスを抑制できる点はメリットです。
特に残業手当に関しては、時間外労働に該当する時間を正確に割り出し、深夜労働や休日労働などの諸条件を加味して計算しなければなりません。労働実態に応じた割増率が誤っていれば、当然ながら算出される残業手当の金額も誤った金額となります。給与計算ソフトを導入すれば、こうした誤りやすい計算で、担当者の負担を軽減できます。
業務を効率化し人件費を削減できる
給与計算ソフトの導入には、業務効率化や人件費の削減といったメリットもあります。給与計算ソフトでは、自動計算による集計が可能になるほか、勤怠管理システムと連携させることで勤怠データを自動で取り込めば、業務時間の削減が可能です。
また、給与計算ソフトを使わない場合、手作業による入力漏れや計算ミスがないか、複数名によるチェックを行うケースは少なくありません。給与計算ソフトでデータを自動で取り込んで給与計算に反映させ、集計も自動で実行できるようになれば、こうしたチェックの工程も簡素化できます。結果として、給与関連業務に必要な人員を削減できたり、担当者の残業手当を抑制したりする効果が得られるでしょう。
法改正などに自動対応できる
給与計算は、税制や社会保険制度、労働基準法などが改正された場合に影響を受けますが、給与計算ソフトであれば改正に自動対応できる点もメリットです。クラウド型の給与計算ソフトであれば自動的に計算プログラムが修正されるため、改正のたびに設定を変更する必要はありません。インストール型ソフトに関しても、アップデートすることで最新の計算プログラムに対応可能です。
例えば、2023年4月より時間外労働に対する賃金割増率の変更が中小企業にも適用されました。具体的には、60時間以上の時間外労働に対する賃金割増率が従来の25%から50%へと変更されています。手作業で給与計算を行う場合、割増率の反映漏れや計算ミスに注意しながら計算しなければなりません。法改正などに自動対応が可能な給与計算ソフトを導入すれば、このようなミスを防ぐ効果が期待できます。
業務の属人化が防げる
給与計算ソフトのメリットとして、業務の属人化が防げるという点も挙げられます。給与計算ソフトは一般的に、専門知識がなくても直感的に操作できるよう設計されています。経理業務の経験が浅い担当者でも対応しやすいため、業務経験が豊富な担当者に仕事が集中し、業務が属人化するリスクを軽減することも可能です。
給与計算は表計算ソフトを用いて作成した集計表で運用することも不可能ではありません。ただし、この場合は給与計算に関する知識に加え、表計算ソフトを扱うための知識も必要です。結果として経理と表計算ソフトの知識を兼ね備えた人材しか給与計算を担当できない状況に陥りがちです。より簡単に操作できるように設計されている給与計算ソフトを活用することで、こうした状況を回避しやすくなります。
給与計算ソフト導入時の注意点
給与計算ソフトの導入にはさまざまなメリットがある一方で、給与計算ソフトの導入効果を引き出すためにはいくつか注意しなければならない点があります。下記の2点を念頭に置いて、給与計算ソフトの導入を検討することをおすすめします。
最低限の給与計算に関わる知識は必要になる
給与計算ソフトは直感的に扱えるよう工夫されているとはいえ、操作する上で給与計算に関する最低限の知識は必要です。給与計算業務では、労働基準法や社会保険、所得税・住民税などの税金に関する基礎的な知識が求められます。
これらの知識が不足していると、万が一ソフトへの入力ミスが発生したり、何らかのトラブルで誤ったデータが反映されたりした際に、間違いに気づけないおそれがあります。
給与計算ソフトは、あくまでも給与計算に関わる業務を効率化するためのツールです。経理に必要な基礎知識が求められる点については、手作業で業務を進める場合と共通しています。
想定以上のコストがかかる場合もある
給与計算ソフトの導入や運用に際して、想定以上にコストがかかる場合がある点にも注意してください。
例えばクラウド型ソフトの場合、初期費用は抑えられるものの月額もしくは年額での利用料がかかり、ユーザー数によって費用が異なるケースもあります。また、インストール型ソフトであれば、導入する端末の数だけ費用がかかるため、まとまった初期費用が必要になることも珍しくありません。インストール型では、アップデートに際して更新料がかかることもあります。
こうしたコストをできるだけ抑えるには、自社にとってクラウド型とインストール型のどちらが適しているのかを見極めることが重要です。一般的にはクラウド型のほうがインストール型と比べて初期費用を抑えられることに加え、アップデートなどの手間がかからないといった特徴があります。担当者の負担軽減についても考慮しつつ、中長期的にどの程度のコストがかかるのか事前に試算し、自社に合ったソフトを精査するのがポイントです。
給与計算ソフトを選ぶ際のポイント
給与計算ソフトを選ぶ際には、自社にとって最適な製品を選ばなければなりません。そのためには、下記の4点を踏まえて選定するのがおすすめです。
目的にあった機能が搭載されているか
給与計算ソフトを選ぶ際のポイントは、自社の目的に合った機能が搭載されているかを確認することです。「従業員ごとの給与額を集計するだけでいい」「Webブラウザ上で給与明細を配布したい」「年末調整に対応可能な機能も欲しい」といった条件によって、選ぶべきソフトは変わります。
給与計算ソフトによっては、勤怠管理機能を兼ねているソフトや、マイナンバー管理などの機能も備わっているソフトもあります。下記の観点で必要な条件を整理し、新たに導入すべき機能の優先順位をつけておくことが重要です。
<目的に合った機能を検討する際の観点>
- ・ 現状のシステムで実現できていて新システムには不要な機能は何か
- ・ 新たに導入する必要がある機能は何か
- ・ できれば利用したい機能は何か
なお、給与計算ソフトによっては対応可能な雇用形態や勤務形態が異なる場合もあります。例えば、契約社員や派遣社員などが混在した複数の勤務形態に応じた計算方法を登録できないソフトや、フレックスタイム制に対応した残業手当の計算ができないソフトもあります。自社での雇用形態や勤務形態に対応した計算ができるか、事前に確認しなければなりません。
既存のシステムに連携できるか
勤怠管理システムや労務管理システムなど、人事労務業務に関する何らかのシステムを導入済みの場合は、給与計算ソフトとの連携が可能かどうかも確認するのがおすすめです。システムを連携できれば、データを自動で取り込んだりデータの一元管理がしやすくなったりするため、給与計算システムを導入する効果をさらに引き出せます。
特に勤怠管理システムに関しては、連携の可否を必ずチェックしましょう。給与計算には残業や休日出勤の正確な把握が必要になるため、日々の出退勤履歴を給与計算システムに自動的に反映させることで、効率化しやすくなります。
連携可能なシステムは給与計算ソフトによって異なります。自社で運用している各種システムとの連携に対応しているかどうか、事前によく確認することが重要です。
担当者にとって使いやすいか
給与計算ソフトを実際に扱うことになる担当者にとって操作しやすいかどうかも、重要なポイントです。新たにシステムを導入したことで担当者が混乱し、かえって業務を進めにくくなるようでは本末転倒と言わざるを得ません。導入するソフトを選定する際には、現場の担当者の意見も聞くことをおすすめします。
ソフトを選定する際には、機能の豊富さがボトルネックになるケースがある点にも注意が必要です。機能が増えることで画面の構成が複雑になったり、必要な手順が増えたりすることもあります。
ソフトによっては無料で利用できる期間が設けられているため、こうした期間を活用して担当者に操作してもらい、より見やすく扱いやすいソフトを選ぶのがポイントです。
サポート体制は十分か
給与計算ソフトを導入する際は、導入時や導入後のサポート体制についても確認することをおすすめします。給与計算に関する業務は給与支給日に間に合わせる必要があることから、万が一の事態が発生したらすぐに対応しなければなりません。操作方法がわからないときや、システムに何らかの不具合などが生じたりした際、迅速に適切なサポートを得られるかどうかは重要なポイントです。
サポートの有無や対応可能な範囲は、給与計算ソフトによってまちまちです。「サポートを得られるのか」「対応可能な範囲やサポート手段はどうなるのか」といった点で不明点が残ることのないよう、十分に確認しておきましょう。例えば、サポート窓口が対応可能な曜日・時間帯や、メール・チャット・電話などのサポートを受けられる手段について、事前に調査することが大切です。
給与計算ソフトを活用して業務の効率化と正確性の向上を図ろう
給与計算ソフトは給与関連の業務を効率化するとともに、正確性の向上を図る効果が期待できるツールです。経理担当者の負担軽減につながるだけでなく、人件費の抑制、業務属人化の防止などにも役立ちます。また、税制や各種法令の改正にも対応しやすくなるため、自社にあった製品を選んで活用しましょう。
NTTデータが提供する達人シリーズには、さまざまな給与計算ソフトと連動して年末調整業務を行える「年調・法定調書の達人」があります。源泉徴収簿や扶養控除等申告書、保険料控除申告書といった各種書類を作成できるほか、給与計算ソフトから給与・賞与データをインポートすることで、入力の手間と時間を削減可能です。
また、費用対効果等の面から一般的な給与計算ソフトを導入していない事業者様向けに、必要最低限の機能だけを厳選した給与計算ツールの達人Cube「データ収集・配信 給与明細オプション」も提供開始予定です。
給与計算および年末調整効率化のため、これらのサービスの活用についても検討してみてはいかがでしょうか。
監修者
石割由紀人(石割公認会計士事務所)
公認会計士・税理士、資本政策コンサルタント。PwC監査法人・税理士法人にて監査、株式上場支援、税務業務に従事し、外資系通信スタートアップのCFOや、大手ベンチャーキャピタル、上場会社役員などを経て、スタートアップ支援に特化した「Gemstone税理士法人」を設立し、運営している。
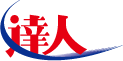


 0120-554-620
0120-554-620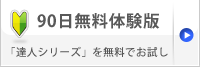
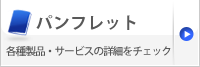
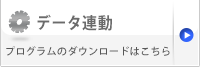
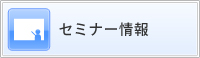
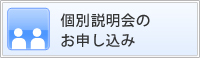
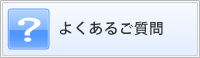
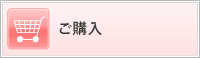
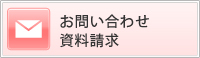




 セミナー情報
セミナー情報 個別説明会のお申し込み
個別説明会のお申し込み よくあるご質問
よくあるご質問 ご購入
ご購入