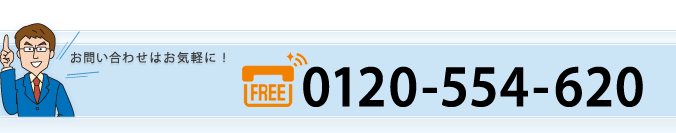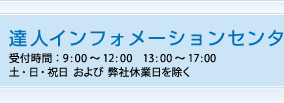一時所得とは?確定申告のやり方や雑所得との違いについて解説

一定額以上の一時所得を得た場合、所得税の納税が必要です。一時所得という言葉は聞いたことがあるものの、雑所得とどう違うのか、どのような場合に確定申告が必要になるのか、具体的に知りたい方は多いのではないでしょうか。
ここでは、一時所得と雑所得の違いや確定申告が必要なケースについて解説します。
目次
一時所得とは、営利目的の継続的な事業や行為以外から得た一定の所得
一時所得とは、国税庁のWebサイト「No.1490 一時所得」によれば「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得」のことです。ここから、一時所得に該当するための4つの要件が挙げられますが、詳細は次の項目「一時所得と雑所得との違い」で解説します。
所得税では所得を10種類に分類して課税していますが、一時所得はそのうちの1つと考えてください。一時所得に該当する所得の例として、下記のような所得があります。
<一時所得の例>
- ・ 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除く)
- ・ 競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く)
- ・ 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除く)や、損害保険の満期返戻金など
- ・ 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除く)
- ・ 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金など
- ・ 資産の移転などの費用にあてるため受けた交付金のうち、その交付の目的とされた支出にあてられなかったもの
- ※ 国税庁「No.1490 一時所得」
一時所得と雑所得との違い
一時所得と雑所得は混同されやすいものの、両者は対象が異なります。雑所得とは、一時所得を含むほかの所得のいずれにも該当しない所得であるため、一時所得か雑所得か迷った場合は、一時所得にあたるかどうかを検討して、雑所得と区別することになります。一時所得ではなく雑所得となった場合、特別控除や損益通算が利用できなくなり、所得金額の課税対象を2分の1の金額とする制度もなく、納税額が大きく変わるため適切に区別しなければなりません。
一時所得に該当するための4つの要件は、下記の通りです。
<一時所得に該当する要件>
- ・ 営利目的の継続的行為から生じていない
- ・ 労務や役務の対価としての性質がない
- ・ 資産の譲渡による対価としての性質がない
- ・ 継続して受け取っていない
この4要件に該当せず、ほかの所得にも該当しない場合には雑所得として扱われます。具体的にどのような収入があると一時所得に該当するのか、例を挙げながら確認していきましょう。
営利目的の継続的行為から生じていない
収入を得るために行った行為が、営利目的の継続的な行為でない場合には、一時所得に該当します。営利目的とは、利益を得るための行為のことを指します。
一例として、競馬の馬券を購入し、払戻金を受け取った場合を考えてみましょう。通常、馬券の購入は払戻金の獲得を目的としているため、営利目的には該当しますが、馬券は1回ごとに購入することから継続的行為とはいえません。仮に予想が的中して払戻金を得たとしても、その所得は一時所得として扱われます。
一方で、過去のレース結果を分析するためのソフトを導入し、配当率の組み合わせによって購入パターンを決めて多数の馬券を自動的に購入する仕組みを整えているようなケースでは、営利目的かつ継続的行為となる可能性もあります。営利目的であり、かつ継続的行為によって生じた所得であれば、一時所得ではなく雑所得としての申告が必要です。
労務や役務の対価としての性質がない
一時所得に該当するには、労務や役務の対価としての性質がないといった要件も満たす必要があります。労務や役務の対価としての性質とは、仕事をしたことへの報酬として金銭を受け取ることを指します。
副業収入として生じた所得であれば一時所得には該当しません。例えば、原稿の執筆を依頼されて報酬を受け取った場合は、それが1回のみの契約で継続性がなかったとしても、執筆という労務の対価になるため雑所得として申告する必要があります。
資産の譲渡による対価としての性質がない
資産の譲渡の対価として受け取った所得は、一時所得には該当しません。このようなケースでは譲渡所得として申告する必要があります。
例えば、不動産や株式、骨董品などの売却に伴って得た利益は、いずれも譲渡所得です。譲渡所得に該当するのは、売上額ではなく利益である点に注意してください。50万円で購入した骨董品が60万円で売れたとすれば、差額の10万円が譲渡所得となります。反対に、50万円で購入した骨董品を40万円で売却したとすれば、利益が出ていないため譲渡所得も0円です。譲渡所得が0円であれば、その取引に関しては確定申告も不要となります。
継続して受け取っていない
一時所得はあくまでも一時的に生じた所得を指すため、継続的に得る予定のない所得が対象となります。生命保険の満期保険金を一時金で受け取るようなケースは、その後継続して保険金を受け取る見込みがないため、一時所得の典型的な例です。一方、年金形式で受け取る保険金に関しては、その性質から所定の期間中は継続して受け取ることが見込まれるため、一時所得ではなく雑所得として申告する必要があります。
また、生命保険に関しては保険料の負担者と保険金の受取人が同一の場合のみ、一時所得として扱われます。保険金の受取人が保険料の負担者と異なるケースでは、贈与税や相続税の対象となる可能性がある点に注意が必要です。
一時所得を得た場合に確定申告が必要になるケース
一時所得によって確定申告が必要になるのは、原則として50万円を超える場合です。一時所得には、特別控除と呼ばれる所得から50万円を差し引ける制度があるため、この範囲内に収まっていれば基本的に確定申告は必要ありません。
なお、資産の損害に対して支払われる損害保険の保険金や、宝くじ・スポーツくじの懸賞金については、金額を問わず非課税と定められています。
一時所得を得た場合に確定申告が不要になるケース
50万円以上の一時所得を得ても、確定申告が不要になる場合があります。下記のように、所得金額によって確定申告の要否が変わります。
所得が一時所得のみで、146万円以下の場合
年間の所得が一時所得のみであり、かつ一時所得が146万円以下であれば確定申告は不要です。
一時所得は、所得金額から50万円を控除したあとの金額に2分の1を掛けた金額に対して課税されます。一時所得が146万円の場合、課税される所得金額は「(一時所得146万円-特別控除額50万円)×1/2=48万円」となります。所得が48万円以下の場合には、基礎控除と呼ばれる制度によって課税される所得が0円となるため、確定申告をする必要はありません。
給与所得者や年金受給者で一時所得が90万円以下の場合
給与所得者や年金受給者の場合、一時所得以外にも給与所得や年金所得を得ていることになりますが、その場合には一時所得が90万円以下である場合に確定申告が不要となります。
原則として、給与所得者や年金受給者は年末調整や確定申告不要制度の対象となるため、確定申告は不要です。ただし、給与所得や公的年金の所得以外の所得金額の合計が20万円を超えていた場合、確定申告をしなければなりません。一時所得が90万円だと、「(一時所得90万円-特別控除額50万円)×1/2=20万円」となるため、この金額を超えた場合には確定申告が必要になります。
なお、勤務先で年末調整を受けていないなど、何らかの事情から確定申告が必要な給与所得者は、金額を問わず一時所得も含めて確定申告が必要です。例えば、年末調整が行われる前にアルバイトを辞めたようなケースが想定されます。給与所得者や年金受給者の一時所得が90万円以下であっても、確定申告が必要なケースもある点に注意が必要です。
一時所得の計算方法
一時所得の基本的な計算方法は下記のとおりです。
<一時所得の計算方法>
一時所得の金額=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円)
このうち「収入を得るために支出した金額」には、当たり馬券の購入金額や生命保険の保険料などが該当します。また、50万円の特別控除は一時所得の合計額から差し引く点に注意してください。1年間に複数の一時所得を得た際には、それらの合計額から「収入を得るために支出した金額」と「特別控除額」の両方を差し引く必要があります。このような計算で求めた所得金額の2分の1に相当する金額が、課税対象です。
なお、一時所得にはふるさと納税の返礼品も含まれます。ふるさと納税の返礼品を受け取っている場合は、ほかの一時所得と合算しなければなりません。一方で、「収入を得るために支出した金額」には、ふるさと納税の寄附金は含まれません。ふるさと納税の寄附金には、所定の金額まで寄附金控除が適用されるためです。
例として、生命保険の満期返戻金とふるさと納税の返礼品を受け取っている下記のケースを考えてみましょう。
<ふるさと納税の事例>
- ・ 生命保険の満期保険金:500万円
- ・ 生命保険の払込保険料:400万円
- ・ ふるさと納税の返戻金の価額:2万円
- ・ ふるさと納税の寄附金額:10万円
この場合、一時所得の金額は「(生命保険の満期保険金500万円+ふるさと納税の返戻金の価額2万円)−生命保険の払込保険料400万円−特別控除額50万円=52万円」となります。寄附金額はこの計算では考慮しません。そのため、課税対象となる一時所得は「52万円×1/2=26万円」です。
一時所得の税率と納税額の計算方法
一時所得は、すべての所得を合算して税額を計算する総合課税の対象です。ほかの所得と合算する際には、一時所得の金額に2分の1を掛けた金額が課税対象となります。
■一時所得の課税のイメージ

具体例で、総所得額の計算方法を確認していきましょう。
<一時所得のほかに所得金額がある事例>
- ・ 一時所得以外の所得金額:20万円
- ・ 生命保険の満期保険金:500万円
- ・ 生命保険の払込保険料:400万円
この場合、一時所得の金額は「生命保険の満期保険金500万円−生命保険の払込保険料400万円−特別控除額50万円=50万円」となり、課税対象となる一時所得金額は「50万円×1/2=25万円」です。一時所得とそのほかの所得を合算した所得金額は「一時所得50万円+一時所得以外の所得金額20万円=70万円」となります。
この金額から、さらに基礎控除や社会保険料控除、生命保険料控除といった各種所得控除を差し引くことで課税所得金額が算出されます。この課税所得金額を下記の速算表に当てはめて税額を計算しましょう。
■所得税の税率にもとづく速算表
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円から194万9,000円まで | 5% | 0円 |
| 195万円から329万9,000円まで | 10% | 9万7,500円 |
| 330万円から694万9,000円まで | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円から899万9,000円まで | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円から1,799万9,000円まで | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円から3,999万9,000円まで | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
- ※ 課税される所得金額は1,000円未満切り捨て
- ※ 国税庁「No.2260 所得税の税率」
速算表で税額を計算したら、住宅ローン控除などの税額控除を差し引き、2.1%の復興特別所得税を加算することで、納税する税額を算出できます。
確定申告書への記載方法
一時所得を含む所得金額を申告する際には、確定申告書の第一表と第二表を作成します。確定申告書 第二表を先に記入し、第一表へ内容を転記するのが一般的な手順です。
なお、懸賞金付き預貯金の懸賞金や、一時払養老保険、保険期間が5年以内など一定の要件を満たす一時払損害保険の差益などに関しては、20.315%の税率による源泉分離課税が適用されます。したがって、これらの所得については確定申告ができない点に注意してださい。
下記では、生命保険の保険料を30万円支払って、満期一時金100万円を受け取ったケースを想定して、具体的な記入例を見ていきましょう。
1. 確定申告書 第二表「所得の内訳」欄の記入
一時所得の確定申告では、最初に確定申告書 第二表に「所得の内訳」欄を記入していきます。なお、第一表・第二表ともに金額はすべて右詰めで記入してください。
■確定申告書 第二表

生命保険料の満期一時金100万円を受け取った例では、「所得の内訳」欄は下記のように記入しましょう。
■確定申告書 第二表「所得の内訳」欄の記入例
| 所得の種類 | 種目 | 給与などの支払者の「名称」及び 「法人番号または所在地」等 |
収入金額 | 源泉徴収税額 |
|---|---|---|---|---|
| 一時 | 生命保険金 | ◯◯◯◯生命 1111111111111 |
1,000,000 | 0 |
なお、生命保険の満期一時金に対する所得税の源泉徴収はありませんが、報酬の種類によっては源泉徴収されている場合があります。下記のような報酬については、支払者に源泉徴収の義務があります。
<源泉徴収の対象>
- ・ 原稿料や講演料など
- ・ 弁護士、公認会計士、司法書士などの専門家に支払われる報酬・料金
- ・ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
- ・ プロ野球選手、プロサッカー選手、プロテニス選手、モデル、外交員などに支払う報酬・料金
- ・ 映画や演劇といった芸能、テレビ放送の出演などへの報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払われる報酬・料金
- ・ ホテルや旅館での宴会で接客を行うホステスなどへの報酬
- ・ プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することによって一時に支払う契約金
- ・ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
2. 確定申告書 第二表「総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項」欄の記入
確定申告書 第二表で「所得の内訳」欄に記入したら、「総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項」欄へ所得の内訳を記入していきます。
■確定申告書 第二表「総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項」欄の記入例
| 所得の種類 | 収入金額 | 必要経費等 | 差引金額 |
|---|---|---|---|
| 一時 | 1,000,000 | 300,000 | 700,000 |
「必要経費等」には、一時所得を得るために支出した金額を記入します。生命保険の満期一時金が収入であれば、記入する金額はその保険について払い込んだ保険料の合計額30万円です。
3. 確定申告書 第一表「収入金額等」の「一時」欄の記入
確定申告書 第二表の「総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項」欄への記入が済んだら、記入した内容を、第一表へと反映させます。
■確定申告書 第一表

第一表の「収入金額等」の「一時」欄に、第二表の「総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項」欄の「差引金額」から特別控除額の50万円を差し引いた金額を記入しましょう。生命保険の満期一時金が100万円、支払保険料の合計が30万円の場合、ここに記入するのは、第二表に記載した70万円から50万円を差し引いた20万円です。
4. 確定申告書 第一表「所得金額等」の「総合譲渡・一時」欄の記入
第一表の「収入金額等」の「一時」欄に記入したら、同じく第一表の「所得金額等」の「総合譲渡・一時」欄を記入していきます。記入する金額は、「収入金額等」の「一時」欄に記入した金額に2分の1を掛けた金額であるため、「20万円×1/2=10万円」を記入します。
5. そのほかの所得や所得控除、税額控除などの記入
第一表「所得金額等」の「総合譲渡・一時」欄の記入を終えたら、一時所得以外の所得や所得控除、税額控除などを記入していきます。すべての項目を記入後、税金額を算出しましょう。
なお、国税庁が提供している「確定申告書等作成コーナー」や確定申告ソフトを活用して申告書を作成すれば、納めるべき所得税額は自動で算出されます。計算ミスや記入漏れを防ぐためにも、このような方法で確定申告書を作成するのがおすすめです。
確定申告ソフトで作成する場合、e-Taxでの提出に対応しているソフトであれば、税務署に出向いたり申告書を郵送したりする手間をかけることなく、自宅などで確定申告書の作成から送付まで完結できます。効率良く確定申告書を作成したい方は、確定申告ソフトの活用を検討してみてはいかがでしょうか。
一時所得と雑所得の違いを理解して、適切に確定申告をしよう
一時所得は、営利目的の継続的な事業や行為以外から得られた一定の所得です。一方で、雑所得は一時所得を含むほかの所得の種類のいずれにも該当しない所得であるため、先に一時所得に該当するかを検討して、両者を混同することのないよう明確に区別することが重要です。また、原則として特別控除額の50万円を超える一時所得に関しては、確定申告が必要になる点に注意しましょう。
一時所得を適切に申告するには、確定申告ソフトの活用をおすすめします。「所得税の達人」は、個人の申告する所得税の申告書・決算書・内訳書やその他の添付書類を作成できるソフトです。総合課税の確定申告だけでなく、申告分離課税の申告や修正申告、準確定申告など、すべての申告書作成に対応しています。e-Taxで申告できる所得税の帳票のうち、98%の帳票を作成することが可能です。また、「電子申告の達人」を活用すれば、「所得税の達人」などの申告書作成ソフトで作成した申告書のデータを電子申告データに変換し、オンラインで提出できます。
一時所得をはじめとする各種所得について正確に申告し、確定申告書の作成や提出をスムーズに進めたい方は、ぜひ「所得税の達人」「電子申告の達人」をご活用ください。
監修者
石割由紀人(石割公認会計士事務所)
公認会計士・税理士、資本政策コンサルタント。PwC監査法人・税理士法人にて監査、株式上場支援、税務業務に従事し、外資系通信スタートアップのCFOや、大手ベンチャーキャピタル、上場会社役員などを経て、スタートアップ支援に特化した「Gemstone税理士法人」を設立し、運営している。
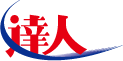


 0120-554-620
0120-554-620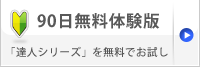
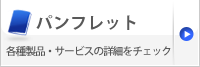
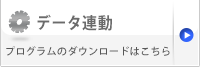
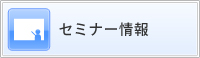
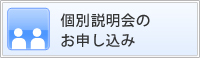
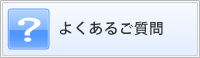
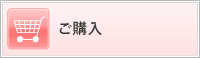
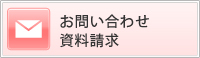




 セミナー情報
セミナー情報 個別説明会のお申し込み
個別説明会のお申し込み よくあるご質問
よくあるご質問 ご購入
ご購入