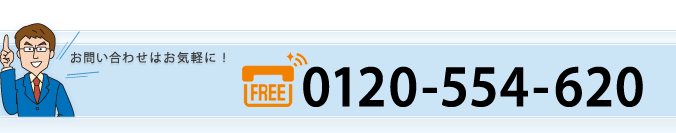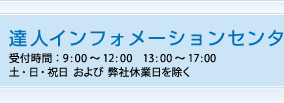消費税の簡易課税制度とは?要件や計算方法、申告方法を解説

消費税には一般課税のほか、簡易課税と呼ばれる課税方式があります。簡易課税とはどのような制度で、どのようなメリットがあるのか整理したいと考えている事業者の方も多いのではないでしょうか。
ここでは、簡易課税制度の要件や計算方法、申告方法などを解説します。
目次
消費税の簡易課税制度とは、中小企業向けに簡単な計算方法を利用できる制度
消費税の簡易課税制度とは、中小企業が消費税の計算を簡易的に行えるよう設けられている制度のことです。
消費税は原則として、「受け取った消費税の額-仕入れなどの際に支払った消費税の額(仕入控除税額)」によって算出します。これが一般課税・原則課税・本則課税などと呼ばれている計算方法です。なお、仕入控除税額を差し引くことは、仕入税額控除と呼ばれています。
一般課税では課税取引や免税取引などを区分する必要があり、仕入控除税額に関しても軽減税率の対象となるかどうかの確認をしなければなりません。結果として、消費税の計算が煩雑になりがちです。
その計算の煩雑さを考慮して設けられているのが消費税の簡易課税制度です。この制度では「受け取った消費税額×業種ごとの一定の割合(みなし仕入率)」の計算式により、消費税をより簡単に計算できます。
■一般課税と簡易課税のイメージ

簡易課税制度の要件
簡易課税制度はあらゆる企業が利用できるわけではありません。制度の対象となるには、下記の2つの要件を満たしている必要があります。
基準期間の課税売上高が5,000万円以下であること
簡易課税制度の要件のひとつは、基準期間の課税売上高が5,000万円以下であることです。基準期間とは、個人事業主の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度の課税期間を指します。また、課税売上高とは、消費税が課税される取引の売上高のことです。
なお、事業者が行う取引には、課税取引のほか非課税取引や不課税取引といった種類があります。非課税取引は、社会政策的な配慮などから課税しないことになっている取引のことで、土地の譲渡や貸し付け、有価証券の譲渡などは非課税取引に該当します。
一方、不課税取引とは、そもそも消費税の課税対象に該当しない取引のことです。給与や寄附金、保険金、株式の配当金などは、いずれも不課税取引に含まれます。
消費税簡易課税制度選択届出書を事前に提出していること
消費税の簡易課税制度の適用を受けるには、事前に消費税簡易課税制度選択届出書の提出が必要です。この届出書は、簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、所轄の税務署へ提出します。ただし、事業の初年度に関しては初年度の会計期間中に届け出れば問題ありません。
簡易課税制度の消費税の申告方法
簡易課税制度による消費税の申告方法には、国税庁のWebサイト「確定申告書等作成コーナー」の利用や確定申告ソフトの利用、手書きによる申告書の作成・提出といった方法があります。それぞれの特徴は下記のとおりです。
確定申告書等作成コーナー
国税庁のWebサイト「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、オンラインで消費税の申告書を作成可能です。消費税の申告書の作成を選択して、基準期間の課税売上高などを入力すると「簡易課税制度を選択していますか?」との質問が表示されます。この質問に対して「はい」と回答し、画面上の指示に従って操作していくことで、簡易課税制度による消費税の申告書の作成が可能です。
「確定申告書等作成コーナー」で作った申告書は、e-Taxを利用して電子申告するか、印刷して税務署窓口などに書面で提出できます。
確定申告ソフト
簡易課税制度による消費税の申告をするためには、消費税の申告に対応している確定申告ソフトを利用する方法もあります。ソフト上で簡易課税制度の利用を選択することで、納めるべき消費税が自動で計算されます。簡単に申告書が作成できるよう、操作画面などが設計されている点がメリットです。
e-Taxに対応しているソフトであれば、電子申告も可能です。また、作成した申告書を印刷して税務署窓口などに書面で提出することもできます。
手書き
簡易課税制度による消費税の申告については、国税庁Webサイトの「消費税及び地方消費税の申告書・添付書類等」より簡易課税用の申告書の書式をダウンロードし、手書きで申告書を作成・提出することも可能です。手書きで作成した申告書は、所轄の税務署へ持ち込んだり、郵送したりして提出します。
手書きで申告書を作成する場合には「課税売上高計算表」をあらかじめ作成しておくとスムーズですが、「課税売上高計算表」の作成には年間の取引を集計する必要があるため、手間もかかります。初めて消費税の申告をする方や、簡易課税制度を初めて利用する方は、「確定申告書等作成コーナー」や確定申告ソフトを利用するのがおすすめです。
消費税簡易課税制度選択届出書の書き方
簡易課税制度の適用を受けたい場合、消費税簡易課税制度選択届出書を作成しなければなりません。
■消費税簡易課税制度選択届出書

- ※ 国税庁「消費税簡易課税制度選択届出書」
届出書の主な項目と記載事項は下記のとおりです。「事業内容」欄に記入する事業区分によって、適用されるみなし仕入率が異なる点に注意してください。みなし仕入率については、「簡易課税制度における消費税納税額の計算方法」の項目で詳しく解説します。
■消費税簡易課税制度選択届出書の主な記載事項
| 項目 | 記載事項 |
|---|---|
| 届出者 | 納税地、氏名または名称および代表者氏名、法人の場合は法人番号 |
| 適用開始課税期間(1) | 希望する適用開始日 |
| (1)の基準期間(2) | 適用開始課税期間の2年前の日付 |
| (2)の課税売上高(3) | 適用開始課税期間の2年前の売上高 |
| 事業内容等 | 自身が行う事業の内容と事業区分 |
消費税簡易課税制度選択届出書の提出方法
消費税簡易課税制度選択届出書の提出には、大きく分けて下記の3通りの方法があります。
<消費税簡易課税制度選択届出書の提出方法>
- ・ 書面を所轄の税務署へ持ち込む
- ・ 書面を所轄の税務署へ郵送する
- ・ e-Taxで提出する
届出書を郵送する際には、普通郵便もしくはレターパックを利用します。届出書は信書のため、宅配便では送付できない点に注意してください。書面提出に使用する書式は、国税庁のWebサイト「D1-4 消費税課税事業者選択届出手続」よりダウンロードできます。
簡易課税制度における消費税納税額の計算方法
簡易課税制度では、消費税額は「受け取った消費税額-(受け取った消費税額×業種ごとのみなし仕入率)」で算出可能です。みなし仕入率と、納税額の計算方法の詳細は、それぞれ下記のとおりです。
みなし仕入率とは、業種ごとに定められた仕入税額控除の控除割合
みなし仕入率とは、「この業種であれば、仕入れにかかる費用はこの程度の割合になる」といった推定にもとづいて定められた、概算の控除割合のことです。業種の区分(事業区分)は第1種から第6種までの6つに分類されており、どの業種に属するかによってみなし仕入率が変わります。事業区分とみなし仕入率は下記のとおりです。
■簡易課税制度の事業区分とみなし仕入率
| 事業区分 | 該当する事業 | みなし仕入率 |
|---|---|---|
| 第1種事業 | 卸売業 | 90% |
| 第2種事業 | 小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業) | 80% |
| 第3種事業 | 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業 | 70% |
| 第4種事業 | 第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業(飲食店など) | 60% |
| 第5種事業 | 運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業に該当する事業を除く) | 50% |
| 第6種事業 | 不動産業 | 40% |
- ※ 国税庁「No.6509 簡易課税制度の事業区分」
納税額の計算方法
簡易課税制度では、課税売上高とみなし仕入率から消費税の納税額を計算します。例えば、第1種事業を営んでいて、課税売上高が1,000万円あり、消費税率はすべて10%の場合の消費税額を計算してみましょう。
この場合、事業者が受け取った消費税額は「課税売上高1,000万円×消費税率10%=100万円」となります。そのため、納付する消費税額は「受け取った消費税額100万円−(受け取った消費税額100万円×みなし仕入率90%)=10万円」となります。
複数の事業区分に該当する事業を営んでいる場合は、原則として事業区分ごとの課税売上高を算出し、消費税額を算出したら、それぞれの事業区分に該当するみなし仕入率を掛けて合計の消費税額を求めます。ただし、1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占めている場合は、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上高に適用することも可能です。
なお、複数の事業区分に該当する事業を営んでおり、事業区分ごとの売上高が計算できない場合は、計算できない部分について最も低いみなし仕入率を適用します。
簡易課税のメリット
簡易課税制度の適用を受けるメリットとして、下記の2点が挙げられます。金銭的なメリットにも繋がる可能性があるため、押さえておきましょう。
計算時の負担を軽減できる
簡易課税制度のメリットは、支払った消費税の管理が不要になるため、計算がシンプルになり事務負担が軽減される点です。
一般課税の原則にもとづいて消費税を計算するには、仕入税額控除を行うために、仕入れなどの際に支払った消費税の額も算出して管理しなくてはなりません。非課税取引などは仕入税額控除の対象にならないため、取引内容によって区分けして管理する必要があります。高頻度で仕入れなどを行う場合、管理が煩雑になることは想像に難くありません。
簡易課税制度の適用を受けた場合、仕入れごとにかかる消費税の管理は不要です。年間の課税売上高をもとにみなし仕入率のみで消費税額を算出できるため、管理や計算の際に要する負担の大幅な軽減が期待できます。
節税できるケースがある
簡易課税制度のメリットとして、節税できるケースがある点も挙げられます。一般課税の方法で算出した場合と、簡易課税制度でみなし仕入率を用いて算出した場合を比較すると、簡易課税制度のほうが多くの仕入控除税額を差し引けるケースもあります。つまり、納めるべき消費税額が少なくなるため、節税につなげることも可能です。
ただし、あらゆるケースで納めるべき消費税額が「一般課税>簡易課税」となるとは限らない点に注意が必要です。実際にどちらが節税につながるのか、試算する必要があります。
簡易課税制度のデメリット
簡易課税制度には、デメリットもあります。下記の2点も念頭に置いて、利用するかどうかを検討してください。
2年間は一般課税に戻せない
簡易課税制度のデメリットは、一度選択すると、原則として2年間は簡易課税制度で消費税の計算をしなければならない点です。例えば、今年度は簡易課税のほうが消費税額を抑えられたものの、翌年度には簡易課税のほうがかえって消費税額が多くなってしまうといったこともありえます。このようなケースでも、2年間は一般課税に戻せなくなるため、慎重に検討しなければなりません。
なお、基準期間の課税売上高が5,000万円を超えた場合は、2年経過していなくても簡易課税制度は適用されなくなります。
税負担が増えるケースがある
簡易課税制度を適用したことによって、かえって税負担が増えるケースがある点もデメリットです。例えば、一時的に支出が増えた期間があった場合でも、簡易課税制度を適用しているとみなし仕入率でしか仕入控除税額を算出できません。この場合は、一般課税で計算したほうが消費税額を抑えられる可能性があります。
一般課税であれば、支払った消費税額が受け取った消費税額よりも大きくなった際には還付を受けられます。一方、簡易課税では受け取った消費税額にもとづいて消費税額を計算するため、消費税額が0よりも小さくなることはありません。したがって、簡易課税制度を適用している限り還付は受けられない点にも注意が必要です。
インボイス制度導入による簡易課税制度への影響
簡易課税制度には、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入に伴い、下記の2つの特例が設けられています。これらの特例により、事務負担や納税額を軽減できる場合があります。
経過措置で課税事業者になる手続きを省略して簡易課税制度を選択できる
インボイス制度の導入に伴う経過措置により、課税事業者になる手続きを省略して簡易課税制度を選択することが可能です。
通常、消費税を納税しない免税事業者が課税事業者になるには、課税事業者になるための申請が必要です。もっとも、インボイス制度の導入時に経過措置が設けられていて、免税事業者が適格請求書(インボイス)を発行する事業者として登録した場合はこの申請は省略できます。
さらに、経過措置の適用を受けた場合、登録開始日を含む課税期間中に消費税簡易課税制度選択届出書を提出することにより、その課税期間から簡易課税制度を適用できます。なお、この経過措置が適用されるのは、2029年9月30日までの日の属する課税期間に限定されている点に注意してください。
2割特例制度と簡易課税制度の有利なほうを選択できる
インボイス制度には2割特例制度と呼ばれる特例が設けられていて、簡易課税制度と比較して納税額が有利になるほうを選択できます。
2割特例制度とは、免税事業者が適格請求書発行事業者として新たに登録した際に、納める消費税額を売上にかかる消費税額の20%とすることができる制度です。この特例は、2026年9月30日までの日の属する各課税期間で適用できます。また、簡易課税制度を選択した事業者は、2割特例の適用を受けるかどうかを申告時に選択できます。
簡易課税制度の納税額は業種ごとのみなし仕入率によって変わるため、2割特例制度と簡易課税制度を比較すると、常に一方の制度が有利になるとはいえません。例えば、みなし仕入率が90%の第1種事業に該当する卸売業の場合、納税額は売上にかかる消費税額の10%となるため、2割特例を適用しないほうが得策です。反対に、納税割合が30%以上の第3種から第6種事業の場合、2割特例を適用したほうが納める消費税を節減できます。
申告時には、事業の状況からどちらが有利になるかを検討しましょう。
簡易課税のメリット・デメリットを押さえて利用すべきか検討しよう
簡易課税制度は、業種ごとのみなし仕入率を適用することで納めるべき消費税額を簡易的に計算するための制度です。基準期間の課税売上が5,000万円以下の事業者であれば、簡易課税制度の適用を受けることで消費税の納税額計算の負担を軽減できるほか、節税につながる場合もあります。一方、簡易課税を一度適用すると2年間は一般課税に戻せないことや、業種や事業の状況によってはかえって税負担が増えかねない点には注意しなければなりません。
一般課税と簡易課税のどちらが節税につながるか確認したい場合は、「消費税の達人」の活用をおすすめします。過去の売上高や翌期の予想売上などの情報を入力するだけで、課税方式ごとの税額のシミュレーションが可能です。これまでに作成・提出した届出書の履歴を登録しておけば、課税方式の適用にあたって提出が必要な届出書を自動的に判定できます。
また、消費税簡易課税制度選択届出書の提出を予定している場合は、「申請・届出書の達人」を活用するといいでしょう。消費税簡易課税制度選択届出書の作成をはじめ、100種類以上の税務関係の申請書、届出書を作成でき、e-Taxによる提出も可能です。簡易課税制度の適用申請や消費税額の算出をスムーズに進めたい場合は、ぜひ達人シリーズをご活用ください。
監修者
石割由紀人(石割公認会計士事務所)
公認会計士・税理士、資本政策コンサルタント。PwC監査法人・税理士法人にて監査、株式上場支援、税務業務に従事し、外資系通信スタートアップのCFOや、大手ベンチャーキャピタル、上場会社役員などを経て、スタートアップ支援に特化した「Gemstone税理士法人」を設立し、運営している。
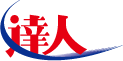


 0120-554-620
0120-554-620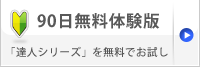
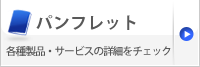
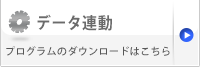
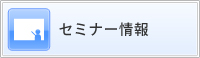
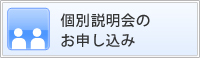
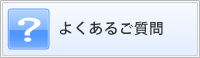
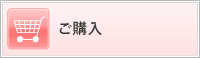
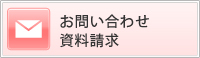



 セミナー情報
セミナー情報 個別説明会のお申し込み
個別説明会のお申し込み よくあるご質問
よくあるご質問 ご購入
ご購入